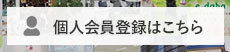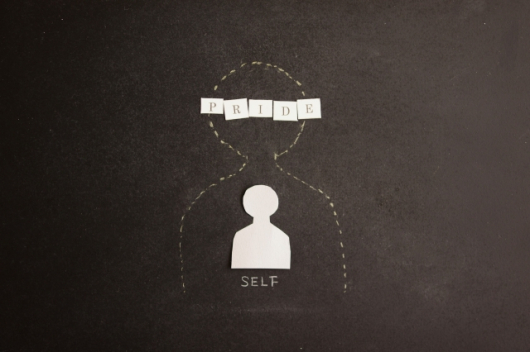ドキュメンタリー映画「普通に死ぬ」監督兼マザーバード代表・貞末麻哉子さんにリモート取材をしました
エンタメ
写真提供 マザーバード
重度障害者を取り巻く現実を描いたドキュメンタリー映画「普通に死ぬ~いのちの自立~」について、監督であり制作プロダクション「マザーバード」の代表でもある貞末麻哉子さんにリモート取材で話を伺いました。
2011年に完成した前作「普通に生きる~自立をめざして~」では、重度心身障害児・者の親御さん達が通所施設を起ち上げる様子を追った貞末さん。昨年夏に完成した今作「普通に死ぬ~いのちの自立~」では、その後8年以上を掛けて取材を重ね、主たる介護者である親が老いや病に倒れると、それまで利用していた通所施設は利用できずに、施設入所が余儀なくされてしまうなど、社会が課す障害が 障害者本人の 地域生活を妨げていく事実を克明に追っています。そして、映画はその後半で、厳しい現実の先に、伊丹・西宮での素晴らしい取り組みを紹介しています。
前作の反省など
──西宮の清水明彦さん(青葉園の元園長)、なかなかすごい方ですね。
「2012年に、伊丹(しぇあーど)の李国本修慈さんが、前作『普通に生きる』の上映会をやってくださったご縁から、清水さんをご紹介いただきました。初めて清水さんにお目にかかった時、この方が園長さんだとうかがって驚きました。外見に偉そうな様子が全く見えなかったのです。お話を少しうかがっただけで、信頼できる存在だなと直感しました。李国本さんも面白い方で、伊丹(しぇあーど)と西宮(青葉園)だけで1本の映画が作れると思って、コツコツ取材をさせていただいてきましたが、『普通に死ぬ』の編集途上で、“個”の力を借りようと思いました。それぞれの施設長が持つ個性的な動きや考えを紹介したいと強く思ったのです」
「当時から、清水さんや李国本さんの伝える内容や言葉は深く心に響きましたが、革新的かつ理論的すぎて逆に難しいと感じる人もいたようです。それがとても残念に思えて、もっとわかりやすくおふたりの素晴らしい仕事と人生哲学を全国の方々に伝えたいと考えていたのです」
──前作から続編である本作へ、主題的にどんな変化が?。
「前作では、障害のある子もその親も、通所施設建設を通して、地域の中で自立をめざしてゆく経過を追いましたが、完成してみると、親さんたちをもっと頑張れ!と励ます映画になってしまわないかという危惧と反省がちょっとだけ残りました。多くの皆さんから「勇気づけられた」「元気が出た」というご感想をいただきましたが、わたしの意図はもう少しその根本の「なぜ親が頑張るしかなかったのか」「地域社会において私たちは何をできたのか」と訴えたかったのです。
続編である本作では、次第に本人も親も年を重ねてゆく中で、医療的ケアの必要な方が2名、施設入所を余儀なくされる事態となってしまいます。非常に苦しい状態に陥る家族の窮状に、なかなか手を差し伸べることの難しい支援側の現実もありました。なぜ社会でなんとかできないのか、なぜ社会は見て見ぬ振りをするのかという思いにさらに強く心が揺さぶられて撮影が長引きました」
「障害当事者の親たちが資金集めから頑張って自分たちの理想とする施設を地域に作ったのに、時の流れの中で、やがて自分たちがその地域で“生ききる”ことのできない現実に直面してゆきます。そんな時、誰が頑張ったらいいのかという問題提起に、親さんのひとりである小沢映子さん(法人設立代表者)が自力で一件目の利用者さんを救出して答えを出します。しかしそれで丸く収めてなんとかなりましたという結末は避けたかったのです」
「そして2件目の利用者さんの入所問題が起こったとき、医療者の立場から坂口えみ子さん(元副所長兼看護師長)の気づきと提案がありました。「親さんのやっておられるケアは、職員も習って担おう」というのが坂口さんの提案でしたが、通所施設でそれを担うにはさまざまな限界がありました。その提案が共に働いてきた職員になかなか理解されない坂口さんはご自身の考えが間違っているのではと思い悩んでおられました。私は何としても李国本さんと、清水さんに会わせたいと思いました。坂口さんにはお二人の話を聞いてもらいたかったし、希望のある現実もあることを見て欲しかったのです」
──本来は地域共生社会として地域で協力するのが理想ですが難しいですね。生きるのを諦める人さえいます。通所型の施設や軽度向けのグループホームは充実してきています。
「重度の方ですと医療の問題がネックになりますからね」
「例えば、呼吸器をつけた状態で病院を退院してきた赤ちゃんの医療的ケアは、自宅に帰って在宅生活を始めた時点からご家族がされるわけです。24時間です。かなり難しい排痰の技術や、神経を使う管理能力が必要となります。状態によっては、片時もお子さんの傍を離れることができずに、親さんは身を犠牲にしてそのケアをされ続けるわけです。
医療技術の進歩によって、この10年で「医療的ケア児」と呼ばれるお子さんは倍以上となり、今や20000人を越えています。親御さんが出来ることは地域で、皆で担っていこう!という坂口さんのメッセージが響いてくれるといいなと私は思っています」
──どうしても家族が中心になって、なかなか周りの支援者などへ広がっていかないですね
「古くから日本では、病気や障害のある家族の介護は、家族がして当たり前という風潮がありますよね。だから、介護離職などという問題も起こってきます。前述の小沢映子さんは、長女・元美さんの障害がわかったとき、小学校の教師を辞めざるを得ませんでした。でもその後、市議会議員になるんです。こうした親さんたちの持つ素晴らしい能力や社会貢献を、介護という現実で家の中に閉じ込めてしまうことは、社会にとっては大きな損失なんです。『何よりも人を大切にする地域の成熟こそが大事なのではないか』と前作の上映の際にも呼びかけてきました。地域づくりは障害者だけのためではなく、やがて自分が障害を持ち、医療の世話になる時のためでもあります。必ず、誰もが老いて障害をもつようになります。他人事ではなく我が事として考えられる想像力を映画から引き出してもらえれば嬉しいですね」
映画に込めた想い

写真提供 マザーバード
──「普通に死ぬ」というタイトルはかなり反響が大きかったそうですね
「最終的に『普通に死ぬ~いのちの自立~』というタイトルに決定するまで随分迷いました。前作は『普通に生きる~自立をめざして~』だったので単純に『普通に死ぬ』ことが一直線上の視野にありました。障害のあるお子さんの親御さんは常に『死』と普通に向き合ってこられているわけですから。しかし、片方では支援者が『死』を忌み嫌う様子に私は違和感を持ちました。生きるために、本当の意味で『死』と向き合わなければ、今を生きる『生』にも向き合えないのではないか。重大な事故を恐れるあまり、医療的ケアの必要な利用者に及び腰な支援に対して親御さんの感じる将来の不安や、流す涙の重さに気づきました。映画を作る人間が『死』から目を背けていたのでは家族や本人の気持ちには寄り添えないのではないかと」
「そして、映画の完成がようやっとみえたところでコロナ禍が始まり、『死ぬ』ということの現実が多くの人にも普通に突きつけられるようになったわけです。そして映画には、『普通に死ぬ』ことを見つめる現実が映っていました。『地域で普通に生活させたい。わが子のために生きなくては』という一心で辛く厳しい治療に耐えることを決心される親さんの姿を見てほしいです」
──「逆に障害を持つお子さんが亡くなられたという親御さんもおられますね。
「『自分が死んだ後、この子はどうなるんだろう』『1日でも長く生きよう』という思いでいたのが、先立たれて初めて違っていたと気付き、『本当は親より長く子どもが生きられる社会であるべきだった』と気づかれる親御さんですね。そもそも、安心して障害のある子を置いて逝ける社会なら親は、先に死ねないとは考えません。親より長く子が生きられない社会ってなに?という話です」
「このご夫妻は、前作では、お子さんの小さい頃は介護で一生を終えるのではと思い、死にたいと思ったことがある、と言われます。しかし一念発起、お子さんが支援学校へ行く間に調理師免許の資格を取り、通所施設の建設に力を合わせ、子どもさんが通えるようになると、自分の店を出して自己実現を目指されます。温かい手料理は地域の財産です。」
「親御さんたちは、お子さんが小さな頃、ほとんどの方が死にたいと思った経験をお持ちです。そして日々介護で精一杯で、ご自身の将来設計になかなか目が向けられずに老いてゆかれます。『親亡き後』という言葉をよく耳にしますが、人生や老後、終末期の生き方にも目を向けて、積極的に親さんご自身の自立や自己実現も支えてゆく支援の必要性を感じています」
今後の展望
──親や周りだけでなく、本人視点の話はありますか。
「清水さんは、西宮で面白い関係性を作られているように感じました。特に、支援者と利用者ご本人さん、経営者、親御さんのあいだで、非常に対等な関係性を築かれているのが興味深いです。今では、ずいぶんとその考え方が全国に定着してきましたが、清水さんや、李国本さんたちがずっと言ってこられている“本人主体”の支援の話はたいへん面白いです。撮影したいのですが、東京から通うことは難しく、こちらにお住まいの方にぜひ撮影をお願いしたいところです」
──制作について気を付けたことはありますか。
「障害者の尊さ“だけ”に焦点を当てた作品づくりは一切しなかったつもりです。このスタンスで作られた映画はそうそう見つからないと思います。かけがえのなさではなく、一緒に生きるにはどうしたらいいかを一緒に考えることができるような映画を作りたかった。そう考えると、登場人物の皆さんから学ぶことの多さに驚かれることと思います」
「また、映画で描く際に一番苦労した部分は、本来なら対立して衝突して汚い言葉も投げ合うことも珍しくない実情です。組織とか、システムとかに組み込まれてしまった施設側と親側の、現実と思いはなかなか折り合いをつけるのが難しく、それでも真摯にぶつかり合う姿(支援会議)から目を逸らすことなく、しっかり撮影させていただきました」
──人に頼らず仕組みを作るべきなのですが、現実は人材が少なく家族にしわ寄せが来ています。
「誰でもやれるかというとそうではない、ではどうすれば地域の中で仕組みとして形成されるかですね。これからの社会は、エッセンシャルワーカーを守れる社会である必要があります」
「コロナ禍によって、“新しい生活様式”などという言葉が行き交って、私たちの多くも、外出できない、人に会えない、不自由な消毒生活を強いられていますが、こうした障害のある人たちのどのお宅には、そもそもどのお宅にもアルコール消毒液があり、ご本人はもとより、親さんたちも自由に自宅を出ることもできません。人にもなかなか会えません。感染対策もあらゆる工夫をされながらして過ごされてきたのです。私たちはこの親さんたちに学ぶことがたくさんあると思っています。一番社会に出てさまざまなことを教えてほしい方たちを自宅に閉じ込めなくて済む社会にしたいですね」
──配信(リモート上映会)などの予定はありますか。
「重い障害のある方が居るとなかなか外に出られないですから、配信のご要望についても把握しています。コロナ禍でなかなか上映会に足を運びづらい状況もありますし、地域の上映会に拘らず、リモート上映会も視野に入れて、なんとか方法を考えてゆきたいと思ってはいます。しかし、これだけ複製の技術が進んでしまうと、安全な配信方法が見つからないのが現実です」
──上映会の拡散やDVD化についてはどう考えていますか?
「一日も早くコロナが収束して地域で上映会を開いていただきたいです。前作もそうですが、こうした映画は地域で上映していただく事に意義がありま。まず主催者の方々が、地域で開かれる上映会の宣伝をされることが地域の交流や理解や刺激につながります。これを配信で済ませてしまうと、交流の生まれる土壌が育ちません。DVDの発売についてもよく聞かれますが、10年はじっくり上映をしてからと思っています。実際に作れば売り上げも大きくてこちらはとても経済的に助かるのでしょうけれども…」
──最後になにか言いそびれた事などありますか?。
「コロナ禍で、また別の意味でも国の指針や考え方が明らかになってきています。そもそも、困難を抱えた人たちの生活をまずどう支えるのか、重い障害のある人たちとそのご家族の生活や人生をどう支えるのか、支える人たちの人材不足や施設運営の現実の厳しさは、国の大きな支援(給付)により解消されてゆきます。国の施策があれば、地域で “生ききる“ ことのできる人がたくさんいるのだということを、もっともっと多くの方に知ってほしいです。 親御さんだけが頑張る社会ではなく、周りや支援者自身も意識を変えてゆきながら、清水さんのおっしゃる“共に生き合う”社会にしてゆきたいですね」
神戸の元町映画館で上映
7月3日から7月9日まで、元町商店街4丁目のミニシアター「元町映画館」にて連日13:10より公開されます。
初日と二日目はリモートにて貞末麻哉子さんの舞台挨拶があり、感染状況をみてからですが最終日は、実際に映画館にて舞台挨拶があります。