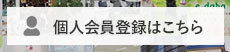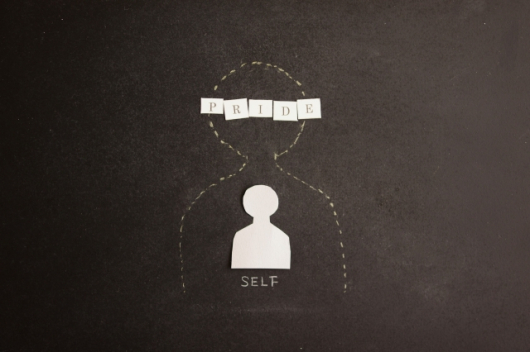優生学をこの世に産み落とした男、フランシス・ゴルトン
暮らし
フランシス・ゴルトン(1822-1911)に対し、あなたはどのようなイメージを抱くでしょうか。聡明で行動力に富んだ彼は、様々な分野でパイオニアとして歴史に名を残します。「近代統計学の父」「指紋捜査や心理テストの創始者」そして「優生学を生み出した男」など、様々な顔を彼は持っています。若い頃は未開拓のアフリカ大陸を横断した冒険家でもありました。
ゴルトンが発明したものは多岐にわたり、現代にも何らかの形で受け継がれているものも少なくありません。良く言えば豊かな行動力を備えた天才ですが、悪く言えば何にでも首を突っ込む出歯亀でもありました。今回は、優生学という怪物をも生み出した男のお話です。
お得意の統計学で口を挟む
ゴルトンは「近代統計学の父」と称されるほど優れた統計学者でありながら、気象図や指紋鑑定などの礎を築くなど多方面に渡って現代に連なる発明を行ってきました。従兄弟には進化論のチャールズ・ダーウィン、遠縁には同じく優秀な統計学者の顔を持つフローレンス・ナイチンゲールがおり、天才一族の生まれであったことが窺えます。
そんなゴルトンが「優生学」を産み落としてしまったきっかけは、従兄弟ダーウィンの出版した「種の起源」でした。これに多大な影響を受けたゴルトンは、お得意の統計学を活かして進化論を独自解釈し始めたのです。これが「優生学」の誕生でした。
1883年、ゴルトンは「eugenics(ユージェニックス)」という造語を打ち出しました。「良い」を意味する「eu」と、「生まれてくる」を意味する「genics」を組み合わせた造語で、これがそのまま「優生学」と訳されています。
ゴルトンの言うユージェニックスは2種類あります。生存に適さない人間を排除するネガティブ・ユージェニックスと、優れた人間を増やしていくポジティブ・ユージェニックスです。ゴルトンは後者を推し進めており、上流階級同士で結婚していくことを是としていました。これはイギリスの階級思想に基づいており、ゴルトンもダーウィンもナイチンゲールも豊かな上流階級に属していたことが背景となっています。
上流階級同士で結婚して子を残し、上流階級の子同士でまた結婚していくというのが、ゴルトンの思い描いた流れだとされています。しかし、ゴルトンは自身の調査で「平均への回帰」を発見しており、この時点で優生学の限界を悟っていたのかもしれません。
外来種
ゴルトンのお膝元であるイギリスでは、優生学は大して流行らなかったそうです。しかし、海を越えた別の国では大流行りし、革命的な思想として迎えられました。優生学が本格的に幅を利かせるようになったのは、1900年代初頭にアメリカへ渡ってからだといいます。関係ないですが、梅毒はコロンブスが持ち込んだという説が有力みたいですね。
アメリカで大ウケした原因のひとつが、「劣化」への不安です。ここでいう劣化とは、移民、知的障害、犯罪者、てんかん、結核、奇形、経済的に自立不可など様々なものを指し、これらを「社会に適応していない特徴」と捉えていました。中でも知的障害は、当時は「精神薄弱」と呼ばれており、IQテストが生まれたばかりで未成熟なのもあって非常に曖昧な基準だったと言われています。
特に問題視されたのがイタリア系などの移民、そして知的障害者でした。これら劣化への不安は政府の介入によって解決されると固く信じられており、1907年には強制断種法が制定されました。1924年の移民規制法よりもだいぶ早い制定で、ネガティブ・ユージェニックスへの本気度が伝わります。
優生学の啓蒙活動も精力的に行われており、優生学的に優れた人間を表彰するコンテストや、「15秒ごとに貴方は劣悪な遺伝子を持つ者のために100ドルを払っている」といった広告などが打ち出されていました。結果、1930年代末までに全米で3万人以上が強制断種を受けたそうです。
このムーブメントを踏襲したのがドイツです。当初は優生学に対し及び腰でしたが、1933年にヒトラー政権が確立されると、アメリカで最も厳しいカリフォルニア州に倣った断種法を制定します。ドイツの断種法は、「遺伝の質を守る」「ドイツ財政を守る」という理由で積極的に支持されました。強制断種は曖昧な理由で横行したためアメリカの約10倍以上に上ったそうです。
ナチスドイツは断種では飽き足らず、約5000人の障害児や約7万人の精神障害者が、生きる価値がないとして殺害されました。同性愛者や結核患者も殺害の対象だったと言われています。そして戦後、ホロコーストを招いた責任を取らされる形で優生学が廃れたのは知っての通りです。主導者たちの多くは戦争犯罪者として処刑されましたが、断種についてはアメリカでもやっていた手前、戦争犯罪に問うことはありませんでした。
優生学はイギリスでは盛り上がらなかったものの、アメリカに渡ると大歓迎されて断種法などの制定に繋がり、その精神と法律はドイツに受け継がれました。そして、過激化の代償として優生学は表向きの破滅を迎えます。ただ、あくまで批判されたのは優生学が生み出した断種法などに対してであり、優生学そのものが糾弾されたわけではありません。
戦後アメリカでは、優生学の思想は医学遺伝学や人類遺伝学へ受け継がれていき、遺伝相談所を開設するなど細々と続いていきました。遺伝相談所の中には、閉鎖された優生学研究所が蓄えていたデータをそのまま相続した所もあったそうです。
やがて「平均」へと帰る
優生学生みの親となってしまったゴルトンですが、適当な放言で終わらせるつもりはなく、正当性を証明するための調査や研究は欠かしませんでした。そこでゴルトンは、自身の生んだものの複雑さに直面させられます。
身長の遺伝をテーマに、高身長の両親とその子どもを調査していたゴルトン。高身長の親から高身長の子が生まれる「正の相関」を把握したまでは良かったのですが、長身の親から生まれた子が親より高身長にならない「平均への回帰」まで見つけてしまいました。平均への回帰は、他ならぬゴルトン自身が名付けた概念です。
「優れた親から優れた子が、駄目な親から駄目な子が生まれるとは限らない」「平均こそ最も生き残りやすいとされ、遺伝子レベルで『平均』へと帰ろうとする」これを知ったゴルトンは、遺伝だけでなく環境や教育も大切だと認識し、「ある人が実際に性能を伝承するには、 才能と熱意と気迫がなければならぬ」と言い伝えたそうです。
それでもゴルトンは自分の生み出した優生学を生涯にわたり推していました。優生学研究への投資は惜しみなく行っており、優生学の信念で出来たユートピアを描いた小説まで執筆していたそうです。死後の出版物には、「優れた人間を増やし、駄目な人間を減らす。その努力を続ければ、集団全体の水準は上がり、天才の生まれる確率は上がる」などと書かれていました。
「ゴルトンの研究や教えが曲解のうえ悪用された」という解釈もありますが、優生学という魔物を産み落としたのは紛れもなくゴルトン自身です。そもそもポジティブ・ユージェニックスを推していたのも、断種や殺戮を認めていなかったのではなく、単に「貧民はわざわざ手出しせずとも自然淘汰される」と考えていただけに過ぎません。ゴルトンの「製造物責任」がいつ取れるのかは、今を生きる我々次第です。
参考サイト
第8章「欧米における優生学とその影響」 飯田香穂里 ジョンズ・ホプキンス大学
フランシス・ゴルトンと「優生学」「平均への回帰」「人格論」
https://s-counseling.com