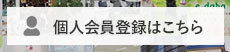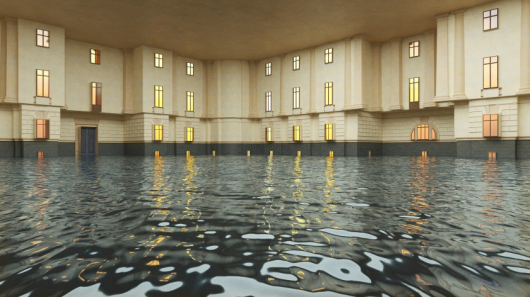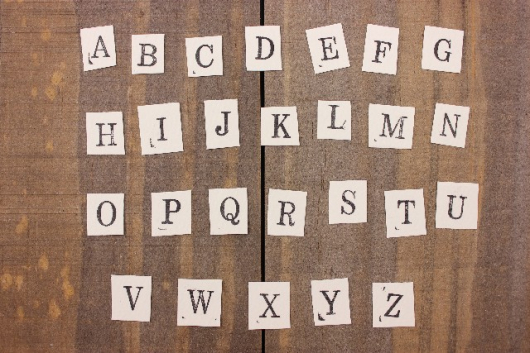エッセイスト小島慶子さんに聞く~1人のADHD当事者として思うこと
発達障害
ADHDと診断され、薬を飲んでみて
──診断を41歳で受けられたそうですが。
「33歳で不安障害と診断され、寛解した後も定期的に通院しカウンセリングを受けるなどしていました。主治医は発達障害も扱っており、カウンセリングで話した過去の困り事の経験などから最終的にADHDの診断が下りたわけです。試しに薬を飲んだ経験を書いた記事を読んだ定型発達の知人らから『ADHDの脳構造について分かった』と言われましたが、何故そう言うのかを自分なりに考察しました」
「もしかしたらそれは、『ADHDの人が定型に近づいた時にどう感じるのかがわかった』ということではないかと思うのです。つまり彼らはADHDではない自身の脳の健在さを認識して“わかった”と感じたのではないかということです。以前、視力の弱い赤ちゃんが眼鏡をかけて喜んだり、聴力の弱い赤ちゃんが補聴器をつけて喜んだりする動画が拡散されていました。見えることや聞こえることを“善”として生きてきた人が、赤ちゃんが視力や聴力を得て“善”に近付いたのを見て『喜ばしい』と感動している訳です。私のことも同様に『発達障害がある脳の人が定型の脳を体験できたのは素晴らしい』と思ったのかもしれません。私は定型発達の人々の脳を体験した訳ではなく、ADHDである私の脳が薬を飲む事によってADHDの特性を抑えられた私の脳になっただけなのですが」 「障害について知ろうとする時には、障害のある人の身体を知ることによって、障害がない自分の身体の有難みを知ろうとしていないか、障害のある人が障害のない人になりたがっているに違いないと思っていないか、その辺りに敏感であることが大事ではないかと思います」
──良かれと思っていたことが本人に良いとは限りませんよね。
「生まれつき視力が極度に弱い赤ちゃんは、ほとんど見えなくても本人なりに母親を感じていた筈です。もともと「見える」ことを知らないのですから、『お母さんが見えなくて悲しい~!』と思っていたわけではないでしょう。眼鏡をかけて、それまで知らなかった「見える」という新しい体験に驚く様子は、確かにとても可愛らしいです。ただ、それを「お母さんを見て喜ぶ赤ちゃんの感動的な動画」として拡散するのは、健常者の驕りかもしれません。見えることが幸福であり、見えないことは不幸であるという前提があるからこその「感動」だからです。私の服薬体験に対する人々の反応にも、同じような構造があったのではないかと思います。こんなことを言うと『折角感動してやったのに素直じゃない!』と思われるかもしれませんね。ともあれ、発達障害に興味を持って私の文章を読んでくれた人が多かったのは素直に嬉しかったです」

自身のADHDと向き合う
──ADHDで失敗してしまった経験は?
「約束の時間に間に合わない、物を忘れる事が多いなどがあります。大きな失敗に、スタイリストさんから事前に預かったテレビ番組の衣装を自宅に忘れたことがあります。スタジオに着て行った服はラフすぎる私服だったので、そのままでは収録に出られません。そこでマネージャーさんに鍵とタクシー代を渡して、急いで私の自宅に衣装を取りに行ってもらったのです。収録が始まる5分前に楽屋に駆け込んでくれてなんとか間に合いました。マネージャーさんは大変だったと思いますが、私のADHDのことをすごく理解してくれていたので、助かりました」
──ADHDだからこそ良かったことはありますか。
「分からないですね。『ADHDだからよく喋る』『ADHDだから書くのが得意』と言われて、そうかなと思ったこともありましたが、言語に対する感覚が鋭いことと発達障害はそもそも別の問題ですよね」
「ADHDでない人生を生きた経験がないので、何が良かったかは分かりません。ただ、相手の話を聞きながら同時に色々な事を考え、即興で議論を組み立てるなどのスキルは、仕事で鍛えられただけでなくADHD特有の気の散りやすさがある程度役立っているのかもしれませんね」
──相手との話に集中できないことはありますか。
「相手の話が面白ければ集中できますが、集中する前に雑音があるとそっちが気になってしまいます。そうなると、よほど話が面白くない限り集中しづらくて困りますね」
──日常の困りごとにはどう対処されていますか。
「締め切りまで二重三重にリマインダーをかけて、工夫しています。しかし、原稿の確認やメールの着信など他のことが割り込んでくると、その分幾つか漏れたり勘違いしたりしがちです。ついさっきまで覚えていた筈のことが蒸発して消えてしまうのです。何かに集中している時に、横から話しかけられたりすると、その内容は特に忘れやすいですね。たとえば執筆中に、画面にリマインダーが表示されても『邪魔だな』と読まずにすぐ消してしまいます。何かに集中している時には、他のことが目や耳に入らなくなってしまうのです」

ADHDと診断されるということ
「診断名が付くにせよ付かないにせよ、ある程度の凸凹は何かしらの表現や探求をする仕事をする人の多くが持っているのではないでしょうか。今の『発達障害』という言葉を通じて、偏りやバランスの悪さに対する慣れ親しみのようなものが広まったこと自体はよかったと思います。その反面、診断名にやたらと拘る人も出てきて、診断名がついたら“普通じゃない人”で、診断名がつかなければ“面白い個性”と線を引くことも。診断は、まともな人がどうかを判別するためのものではなく、必要な支援につながるためのものだと知って欲しいです。また一方で、自己診断でADHDは天才の証であるかのようにいう人もいますよね」
──ADHDを自称するような感じですか。
「診断名を、駄目な人ラベルとして使う人もいれば天才ラベルとして使う人もおり、正しく知ろうとする気持ちが足りないと感じることがあります」
──診断は支援を受ける基準として大切でもありますよね。
「診断はその人自身の困りごとを軽減するためのものであって、他人から見て「普通ではない人」をわかりやすく区別するためのものではありません。自分や我が子に『障害』という診断が下るのを不安がるのは、ラベルとして見ているからかもしれません。一番大切なのは、困りごとが減ることですよね」

エッセイストとして考える「障害」の表記
──エッセイストとして「障害」「障がい」の表記についてはどうお考えでしょうか。
「『障害の社会モデル』というように、その人にとっての“障害”は社会の側にあります。そういう意味で、私は『害』という表記を、“他の人の害になる者”とは読みません。『害』の字は、社会の側に障害者を排除するような仕組みが未だに残っていることを示しています。もちろん、ひらがなで書いてほしい人の気持ちは尊重しますが、私自身はそう捉えています」
「発達障害について知ること自体は非常に大切なことなので、知ろうとする人が増えるのは良いことだと思います。いま発達障害に対する考え方の一つに『ニューロダイバーシティ(神経の多様性)』という概念があります。正常と異常で分けるのではなく、脳の特性を様々な多様性として捉えるアプローチです。それに加えて、先述したように、『どうすれば困りごとを少しでも減らし支援に繋げられるか』という発想で考えて欲しいなと思います」
「発達障害者と一緒に生きていく社会は、『発達障害のある厄介者を仲間に入れてやる社会』ではありません。自分にはない困りごとや不便さを抱える人と、同じ空のもと生きていくうえでどのような仕組みがあればいいかを考えて欲しいです。お互いが嫌な思いをせずに安心して生きていくために知恵を絞ることが大事ですよね」 「日本では発達障害をタブー視し、ネガティブなイメージで語ることが多いですが、オーストラリアでは、ADHDもASDもLDも居て当然という認識です。例えば発達障害のある子には期末テストの時間が15分多く与えられます。それは視力の弱い子が眼鏡をかけるのと同様のこととして捉えられているので、他の生徒が『ずるい』と文句を言うことはありません。息子の通う大学では教授や友達が自然な会話の中で『自分はADHDだ』と話しています。言っても差別や攻撃を受けるような環境でないため言いやすいのでしょう。日本もそうなるといいなと思います」
──最後に伝えたいことはございますか。
「障害はひとりひとり違いますよね。私はインタビューや連載で自分の体験を語っていますが、ADHDの代表ではなく、数多くいるADHDを持つ人の一人に過ぎません。ましてや専門家でもないので、どうか私の話を一般化しないで読んで欲しいです。より多くの人の個人的な体験を聞くことで、『ADHDも人それぞれ』と分かります。その一例として私の体験を知ってもらえたら嬉しいです。今、自分の場合はこう、と発信する人が増えているのはとてもいいことだと思います」
「もちろん、話したくなければ話さなくてもいいです。話す時には『自分の場合はこうだ』となるべく具体的に話すほうがいいと思います。同じ診断名でも人それぞれに実感が違うことを一言付け加えれば、診断名ではなく個人を見るべきであること、診断名がその人の一部にすぎないことも分かるのではないかと思います。そうやって理解が広まっていくといいなと思います」

小島 慶子(こじま けいこ)
1972年、オーストラリア・パース生まれ。タレント、エッセイスト。東京大学大学院情報学環客員研究員、昭和女子大学現代ビジネス研究所特別研究員。1995年、学習院大学法学部政治学科卒業、TBS入社、アナウンサーとしてテレビ・ラジオに出演。1999年、第36回ギャラクシー賞ラジオ部門DJパーソナリティー賞受賞。2010年、独立。各種メディア出演、執筆、講演など活動の幅を広げ、現在に至る。