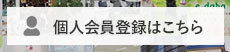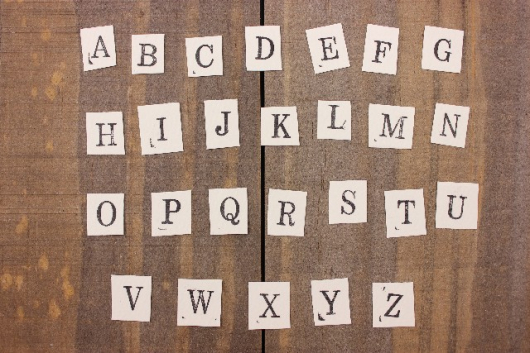映画の中の障害者(第10回)「市子」
エンタメ
Photo by Geoffrey Moffett on Unsplash
絶賛ほぼ一色のミステリードラマ
今回は2023年12月に公開された戸田彬弘監督「市子」を取り上げます。元々舞台の戯曲「川辺市子のために」の映画化で、主演は朝ドラなど活躍目覚ましい杉咲花。貧困世帯で生きるミステリアスな女性を変化自在に見事に演じ、本作最大の見どころとなっています。
周辺の映画ファンや町山智浩など信頼する評論家らが「今年ベスト!」など絶賛一色なので期待して見たのですが、正直困惑させられて、確認するために2回見終わった後ファミレスで書き連ねています。演者の素晴らしい演技はじめ諸々ハイクオリティなのですが、看過できない問題も大きく、複雑な感情をぶつけた考察で不快になる方もいるかと思いますが、拝読いただけたら幸いです。
※以下ネタバレあります(ミステリー作なので、鑑賞予定の方は鑑賞後をお薦めします)
人間・社会の影に光を当てる
川辺市子(杉咲 花)は、3年間一緒に暮らしてきた恋人の長谷川義則(若葉竜也)からプロポーズを受けた翌日に、突然失踪。途⽅に暮れる⻑⾕川の元に訪れたのは、市⼦を捜しているという刑事・後藤(宇野祥平)。後藤は、⻑⾕川の⽬の前に市子の写真を差し出し「この女性は誰なのでしょうか。」と尋ねる。市子の行方を追って、昔の友人や幼馴染、高校時代の同級生…と、これまで彼女と関わりがあった人々から証言を得ていく長谷川は、かつての市子が違う名前を名乗っていたことを知る。そんな中、長谷川は部屋で一枚の写真を発見し、その裏に書かれた住所を訪ねることに。捜索を続けるうちに長谷川は、彼女が生きてきた壮絶な過去と真実を知ることになる。
(本作公式ページより)
監督も述べているように黒澤明の「羅生門」のように複数の証言から「市子」という人間を浮き上がらせる構成で、小学・高校時代の同級生の視点など、一筋縄で行かない人間の多面性と彼女を取り巻く社会が描かれます。
市子は無戸籍児なのですが、姉に戸籍があり、知的障害とだんだん筋力が衰える筋ジストロフィーで寝たきりの月子がいる設定です。そして市子は、体が弱くなる月子になり代わり小学校へ通います。この辺は、私は一人暮らしで24時間の公的介護サービスを受けて精力的に活躍している筋ジストロフィーの友人など見ているので「ん?」となってしまいます。ただ、福祉サービスをまるで無視した貧困&知的障害者を描いた「岬の兄弟」(2019年)同様、人間の本質を描くためにあえて現実を改変するのは、覚悟を持って描くなら許されると思います。逆に言えば、その覚悟が本作の問題にもつながります。
消された障害児の姉
出演者の熱演や巧みなカメラワーク、徐々に明らかになってくる市子の姿に眩暈がする前半と比較して、映画は後半失速していきます。市子が養父に襲われるあたりから、紋切り型・記号的な不幸描写のオンパレードで監督の社会経験知の低さが露呈していきます(この辺は以前取り上げた「ミッドナイト・スワン」(2020年)と酷似)。「奥能登に逃亡した母が男と痴話喧嘩」「ネット掲示板で自殺志願の女」「介護疲れの尊属殺人」等々…このへんが都合良くダイジェスト的に展開していき、どんどん醒めていきました(ただ、杉咲花の演技力が半端ないので、誤魔化されてしまう)。そして、本コラム的にも特に看過できないのが、終盤市子に殺されて山中に埋められてしまう障害児の姉・月子の扱われ方です。
複数視点で市子が浮き彫りになるのですが、肝心の市子同様「痛ましいほどの過酷な家庭環境で育ちながらも、『生き抜くこと』を諦めなかった」(byパンフレット)はずの姉・月子の視点はありません。本作では、月子は「不幸の根源」として非人間的な存在である必要があり、それゆえ、この冷酷さと前述の表層的な不幸描写が相まって「結局弱者をバカにして面白がってるだけ」という感覚を強めます。
介護に疲れて殺害してしまう描写が問題ではなく(ここ自体は凄まじかった)、どうしてかつてあったはずの家族の絆が消え、血のつながる姉妹の情が消えたのか、一番それを見て感じてきたはずの月子視点を描くべきだったのではないでしょうか。そうすることで市子や映画により膨らみが持てたと思うのです(具体的には自殺志願者の北見冬子視点を外して、その分、市子と月子の関係を掘り下げて欲しかった)。それなのに、この尊属殺人という重大な罪は母親が泣きながら「色々限界だったの」というセリフでまとめてしまい、この軽さに愕然としました。
繰り返しですが、障害者が悲惨に扱われているから問題なのではなく、この乱暴で雑な描かれ方が映画全体の「軽さ」を象徴していると思うのです。ラストの夏祭りのささやかな市子の幸福を描くくだりも、同情できないサイコパスの一側面としか見れませんでした。 ※ちなみに舞台では「川辺月子のために」という続編があるそうです。内容は不明なのですが、ここで述べた問題点を解消するようなものなのかも知れません。映画がヒットしたのならスピンオフ「月子」を期待します。
炭鉱のカナリア
普段目にしない、または目を逸らす社会や人間の影に光を当てるのが表現の役割の一つだと思います。しかし、本作で描かれて寄り添っているのは、あくまで尊属殺人犯であり、殺された障害者ではありません。1970年に母親が知的障害と重度障害を持つ子を絞殺した事件があり、母親に同情的だった世間に猛然と抗議したのが脳性マヒ者による団体「青い芝の会」です。そういう視点からも、弱者に寄り添っているようで、実は強者視点で世間的に受け入られやすい作品です。結局、相変わらずサブカル界隈の弱者の「生きている姿」を見て見ぬ振りする冷酷さに疲弊したのが偽らざる感想です。
今年に入って、相模原連続殺傷事件を扱った「月」同様、障害者を殺す側に寄り添った映画が立て続けに作られていて、それなりに話題になっていることに危惧を感じます(「月」については、時期を改めて考察を掲載できたらです)。もちろん、上部だけの多様性の偽善に抗う表現はあって然るべきなのですが、その手段として「障害者殺し」というのに「軽さ」「浅ましさ」を感じます(なんか中学生が「世界には正義も悪もないんだよね」とイキってる気恥ずかさ)。ポリコレ疲れへの反動として「月」「市子」は各種映画賞を席巻する可能性があり、注視しています。
(参考リンク) 「市子」公式サイト
https://happinet-phantom.com/ichiko-movie
https://ja.wikipedia.org/