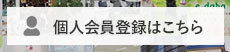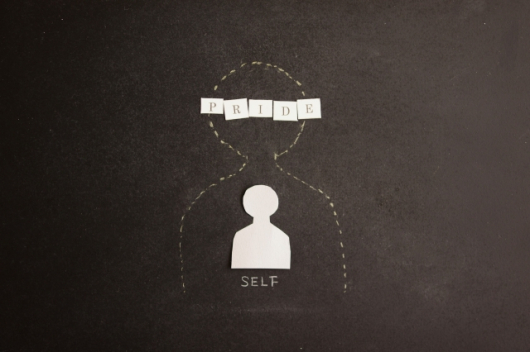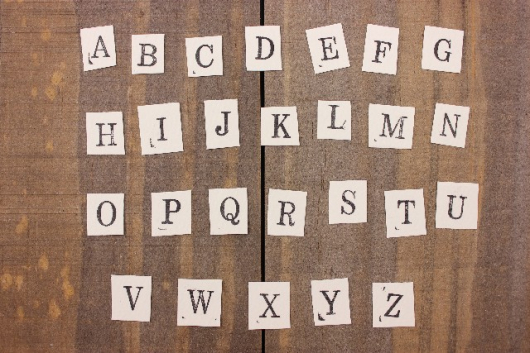聖路加国際病院の牧師による性暴力事件で賠償命令。判決を前にシンポジウムを開催
暮らし
聖路加国際病院で難病治療に伴うメンタルケアを受けていた女性患者が、スピリチュアルカウンセラーである牧師(チャプレン)から性暴力を受けていた問題で、牧師と聖路加国際大に計約1160万円の賠償を求める民事訴訟がありました。2022年12月23日に東京地裁の判決が出ており、110万円の賠償が命じられています。
判決の出る2週間ほど前の12月6日、この性暴力事件に関するシンポジウムが開かれました。4人の専門家がそれぞれの職業的観点から熱く語っており、キリスト教施設における性暴力問題について考えていく時間となりました。
聖路加国際病院は患者ファーストと言われていましたが、そこですら医療従事者から患者へのハラスメントに対する意識は低いです。患者からのハラスメントには対策が強化されている反面、患者がドクターハラスメントを受けるリスクについては放置されているばかりか、患者の立場が年々弱まりハラスメントが潜在化しやすくなっています。
性犯罪の告発に立ちはだかる2つの壁
神奈川県弁護士会に所属する本田正男弁護士が本件について、次のように話しています。原告は2017年5月の入院中、メンタルケア担当の牧師(チャプレン)から性暴力を2度受けました。病院そのものに対しフラッシュバックを起こすほどになったので救済を求めましたが、病院では救われないどころか二次被害まで受けます。
性犯罪の告発は、ネットやSNSの進歩でやりやすくはなったものの、依然2つの壁があります。ひとつは証拠が無くて事実を否定される壁、もうひとつは証拠があってもなお被害者の落ち度を責められる壁です。立場としては加害者側の方が圧倒的に強く、対等な関係などあり得ません。キリスト教という権威や組織構造が、加害者側の開き直りを促しているのではないでしょうか。医者同士や弁護士同士にもあるようなかばい合いの体質があるのではないでしょうか。頑としてかばい合う体質は、見ただけでも被害者にとって心労になります。牧師が性犯罪をしながら日常を謳歌する現実があります。実際、刑事訴訟が不起訴になったのをいいことに、刑事と民事をわざとごっちゃにして自らの潔白を訴えている始末です。
性暴力被害者に寄り添う支援が必要
性暴力被害者のアドボケイト活動を行っているTRCC(東京強姦救援センター)の織田道子さんは、次のように話しています。
「強姦」は報道で自主規制になるほど強い言葉で、使えるなら罪名か固有名詞くらいでした。それが「東京強姦救援センター」の名の由来です。有耶無耶な言い換えでは性犯罪の実態が伝わらないのです。
我々にとって性暴力とは、望まない性行為すべてを指します。目指すのは、女性として被害を共有し、被害者の自立をサポートする裏方としての役割です。
スタッフは相談員や医師や弁護士などを含め、40時間ほどの適性チェックをパスした女性だけで組まれています。適性チェックはかなり厳しく、少数精鋭でもあります。活動はほぼボランティアで、報酬はすべて支援活動に充てられています。
特に弁護士は完全に被害者側へ立つという規則があり、どんなに優秀でも加害者側の弁護経験があるならお断りしています。加害者側に女性弁護士が付くと、女性が女性を責めることになるので、被害者は心証が悪くなるし精神的にも摩耗します。仕事の幅が狭くなっても被害者だけを弁護するという志を持った弁護士が30人弱は属しています。
支援について、まずは上下関係を作らず対等に接するのが大前提となります。そして、完全に被害者の側に立たねばならす、少しでも被害者を疑うようなら支援する資格はありません。その為、性犯罪に対する偏見を排除する等のトレーニングを積みます。
被害を疑ったりジャッジしたりと自己判断はせず、被害者の望みを一緒に探します。支援者は自分に出来ることと出来ないことを弁別して、被害者に伝えます。望まれる支援を全てやるのは無理ですが、望まない支援をしないことで二次被害を防ぐことが出来ます。
支援には被害者心理の理解も欠かせません。被害を信じてもらえないのではないか、自分が原因ではないかという不安は誰もが抱えています。
「理不尽な体験で心が折れて意欲が湧かない」「支配を拒み主張を曲げない」「話がズレたり攻撃的になったりする」「同じ意見でなければ相談相手を否定する」と色々な反応はあるが、性被害が下地になっている以上は仕方がありません。ただ、被害者自身にとってマイナスになる提案(犯罪など)は止める。過去に、証拠を集めようとしたら加害者から逆に訴えられて負けた人がいます。
裁判で被害は解決しないというスタンスなので、本人が望まない限り裁判は勧めません。裁判中心の生活になれば生活基盤が壊れていくからです。そのため、裁判で予測されるマイナス面は必ず伝えておきます。
判決は裁判所が出すので望み通りにはなりませんが、事件を公の記録に残し人々に知らせることなら出来ます。本人尋問で直に主張も出来ます。しかし裁判でも被害者感情だけは解決できません。被害者の支援は一生続くのです。
メンタルケア従事者による患者への性暴力の実情と課題
市民の人権擁護の会日本支部の米田倫康さんは、医師やカウンセラーなどの専門職による性暴力の課題を指摘しています。
この事件の加害者であるスピリチュアルカウンセラーは、精神科医を補う専門職として役割を担っています。それが性犯罪者になるのは衝撃でした。
医師でも性犯罪は罪に問われますが、実際は様々な抵抗があります。「医師免許の自主返納で有罪を免れようとする」「有罪が確定しても行政処分まで医師を続ける」「免許を剥奪されてもなお医師を続けて捕まる」「示談や不起訴や起訴猶予で首を繋ぐ」「治療行為の一環と言い張り無罪に持ち込む」
カウンセラーもまた係争中の事件さえありますが、国家資格持ちへの行政処分は今のところ一例もありません。
最大の団体となる日本精神神経学会では、2014年に倫理綱領を作り2021年に細則を入れ、具体的に精神科医の性的接触を禁じました。背いたところで刑事罰はありませんが、民事訴訟には客観的な基準として使えます。日本スピリチュアルケア学会でも、具体的な規則を設けていますが、どのみち民間団体の倫理綱領に過ぎないのがネックです。
例えば弁護士なら弁護士会に属さないといけないし、弁護士会で懲戒処分を下せます。医師は学会や医師会に属さなくてもいいですが、国が処分を下せます。しかし民間団体は、内規による追放はあるかもしれませんが、実際は無所属のカウンセラーとして続けられるのでノーダメージとなります。
法律にも限界があります。実際に、何十人にも手を出して2人自殺に追いやった精神科医が鹿児島にいましたが、現行法では何の罪にも問えず、別件で診療報酬の不正を暴いて詐欺罪で訴えてようやく免許剥奪に至りました。「精神科医の地位を悪用して患者と性的関係を持つのは、医師の品位を損なう行為ではないのか」と厚労省に何度も問い合わせている最中です。
根本的な解決には、法律自体が変わらねばなりません。刑法に引っかからなければ行政処分も起きないからです。ドイツの刑法やイギリスの性犯罪事例を参考にするならば、治療に携わる人が患者と性的関係を持った時点でアウトという単純な話になっていますが、その単純明快な法律に倣うだけでも障壁は多いでしょう。この裁判が持つ意味は大きいといえます。
日本同盟基督教団の取り組み
被告自身が認めているにもかかわらず、被告の属する日本基督(キリスト)教団などはこれを放置したままです。この不誠実な対応も原告の精神的苦痛となっており、提訴に踏み切った一因でもあると思います。法廷闘争を選んだ原告には敬意を表します。
日本のキリスト教でプロテスタントの信者は約60万。教会は約8000、教団は150あり、各々が自治を持っています。別々の教団を跨いで牧師になることはありませんし、相談窓口も教団ごとに別々です。性暴力含むハラスメントを相談できる教団は少ないですが、牧師への回帰委員会を設ける教団は多いです。それにしても、教師が生徒と関係を持つのは問答無用で処分できるのに、なぜ牧師には出来ないのでしょうか。
日本同盟基督教団では、回帰委員会と別に人格尊厳委員会も設けており、そこでは相談者を第一に考えて仕事しています。相談者の意見を大切にし、疑ったりジャッジしたりせず、客観性を維持するために相談者と牧師の意見は別々の人が聞くなど工夫をしています。ハラスメント事実が認められれば、二者の関係調整に移り、大抵は牧師への更生プログラムが入ります。調査権限が無いので出来るのは聞き取りと審議だけですが、事例の発生から相談までの期間制限はありません。日本同盟基督教団人格尊厳委員会の大杉至さんは、次のように話しています。
性暴力事件の責任は加害者だけにあるのですが、被害者を責める者もいます。不起訴や無罪判決は司法の問題であって、被害者に落ち度はないのですが、「加害者が潔白で被害者は噓つきだ」と加害者本人は兎も角、周囲までそう囃し立てるのは如何なものでしょうか。加害者の取り巻きは、加害者自身に内省と行動変容を促すべきではないのでしょうか。見て見ぬふりをするのではなく、間違いを糺し反省させるのが、友達としてあるべき姿だと思います。
キリスト教は「愛と罪と赦し」の宗教と言われますが、性加害者への許しを強要するのは違うのではないでしょうか。だいたい「罪」も社会的な意味ではなく、神に対する罪を指すものであり、「赦し」とは神との和解を意味します。人への罪は「悪」であり、それは「償う」必要がある。この辺りが聖職者ですらごっちゃになっています。
どの教団もポジション争いに集中していて外の世界に関心が無いように見えます。自治の壁を壊すには教団の内外から声を上げることが重要ではないでしょうか。キリスト教系は国家権力の介入を嫌う節がありますが、自治を重んじるのであれば、そのぶん己を律していかねばなりません。
「私の事件で最後に」被害者女性の切実な訴え
原告である被害者女性は、判決前に開催されたシンポジウムの中で、「私は被害に遭ってから誰からも謝罪をされたことがありません。被害を否定されたりこちらの落ち度を問われたりして、自分の感性を疑いさえしました。被害を申告する中で散々な対応を取られて誰も信じられなくなったのが私の二次被害です。本当に警察の捜査がなければ今生きていなかったかもしれません」と語っています。
「他人のカルテを出されたりクレーム担当者に捕まったりと、病院は信用ならないので築地警察署に助けていただいた次第です。病院の人は誰も助けてくれないし信じてもくれない、やる事といえば加害者を軽くヒアリングしただけで、事件を矮小化しようとしていましたし、私が本来必要とする難病治療さえ中止寸前となりました。教団も加害者である牧師に『守る会』を結成してまで肩入れしています」と病院に対する不信感は増すばかりです。
「この5年間、教団はただ責任転嫁と見て見ぬふりをしてきただけで、ハラスメントの有無を調査するかどうかすら怪しいです。教団や教派を越え、キリスト教全体で調査をして、私の事件で最後にしてもらいたいです」と被害者女性は強く訴えてシンポジウムは締めくくられました。