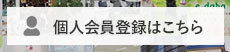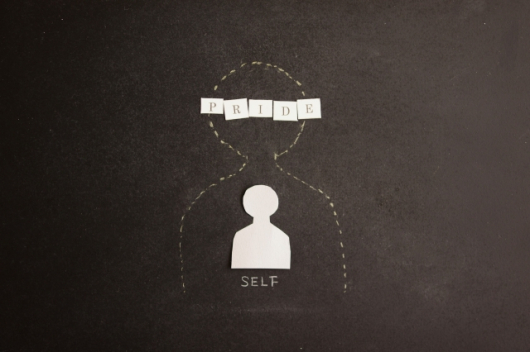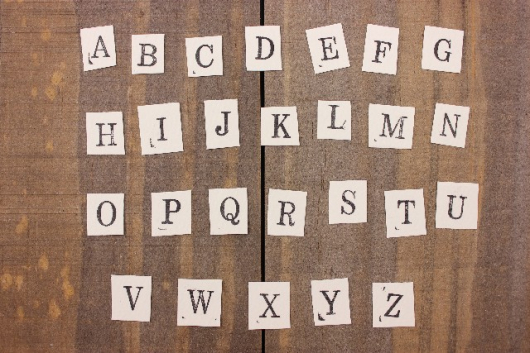発達障害文学〜文字を打ちなよ
エンタメ
最近は、発達障害当事者の人生と想いをつづった著書が注目されています。代表作としては、『自閉症の僕が跳びはねる理由』の東田直樹さんが有名だと思います。大学時代に私は勉強の一環で当事者の著書を読んでいました。その中で、特に女性の発達障害者の自伝書に心を打たれました。まさにその方の「人生」という名の「物語」でした。今回は「女性の発達障害」の本で共感を抱けた点などを、私自身の体験もふまえて紹介します。
本当の自分を見つけて
まずは、ドナ・ウィリアムズさんによる『自閉症だったわたしへ』を紹介します。内容は、淡々とした文章でありながらも、独特な哲学が美しくつづられています。それは小説を読む時に感じる心の静けさや、ほどよい緊張感を与えてくれます。ドナさんは幼少期から大人で自閉症の診断が出るまでの間、自身の感じてきたことや直面してきた困難、そして優しい人々による支えについて語っています。子どもの頃からドナさんは、両親から心理的な虐待、学校や外でも周りにいじめられ、「ドナはくるくるぱー(頭のおかしい子)」と呼ばれて育ちました。人と上手く付き合えなかったドナさんは、やがてウィリーという皮肉屋のキャラで母親の暴言に耐えたり、キャロルというおしゃべりで社交的なキャラで周囲と楽しくなじもうとしたりします。
私自身も昔から周りに「変わった子」だとか「あなたは人の嫌いなことが好きだね」、と言われ、家の外ではいじめや叱責を受けてきたので親近感がわきました。さらにマンガやアニメの世界にこもっていた私は、好きなキャラの口癖や態度を真似ることで、人付き合いに対処していました。しかし、ドナさんも作中でも語っていますが、本来の自分とは違うキャラで人と接し続けることには限界があります。複数のキャラを被って人間関係に対処することは、有効な場合もあれば、トラブルの原因になることもあります。ドナさんの場合、来るもの拒まずのキャロルのキャラで対応していた結果、行きずりの男にお金や仕事を奪われるなどの被害にも多くあいました。ドナさんは特性や周囲との関係で悩み、苦しみ、医師や先生、支援者、同志との出会いを経て、彼女は自分が「自閉症」であるという人生の答えの一つに、自ら辿り着いたのです。診断発覚後は、世界中で自閉症の講演会を開き、発達障害児の療育から、著作、絵画、音楽、彫刻などの芸術面でも幅広く活動しています。
本書の原作タイトルは、Nobody Nowhere(誰でもない。どこでもない)です。それはドナさんに限らず多くの発達障害者が抱える、「社会のどこにも所属できず、社会に受けいれられる誰かにもなれない」、という心の叫びがあります。しかし、多くの出会いと困難を経てドナさんは、Somebody Somewhere(どこかにいる、誰か)になれました。最終的にはAnybody Anywhere(どこにでもいる誰か)になることを目指しています。これは障害者の方の「普通になりたい」、「普通に生きたい」という切実な願いを表現していると思います。
死と苦痛からのサバイバー
次は、Lobin.Hさん(日本人)の『無限振子 精神科医となった自閉症者の声無き叫び』を紹介します。医者ということもあり、本自体は比較的薄く、章ごとにまとめも書いてあるため、非常に読みやすいです。Lobinさんは自閉スペクトラム症のある精神科医です。ドナさんと似た高機能自閉症のタイプであるため、大人になってから自身が発達障害であることを理解しました。さらなる類似点は、Lobinさんも両親に支配され、いじめや友人関係に悩んだ末に、人間嫌いの厭世的(えんせいてき)なキャラや、社交的なハイテンションキャラなど、複数の顔を被って生きていました。Lobinさんは、医学部入学から卒業後に精神科医として働いていた時も、人間関係のトラブルやデートDVを含む被害など多くの苦難がありました。そしてあることがきっかけで、遂に自殺未遂で一度生死をさまよいました。
私の場合、母親を含む優しい人たちに昔から恵まれました。生きている中で、私も何らかの被害にあいかけたことがあったと思います。ですが、運良く深刻な被害にあったことは今のところありません。もしも私に味方がおらず、周りの悪い人達と運悪く関わってしまった場合、Lobinさんを含む多くの女性の発達障害者が受けたのと同じ、悲惨な被害にあっていたと思うとぞっとします。その後意識を取り戻したLobinさんは、医学部時代からの恩師による治療とカウンセリングを受けて、少しずつ回復してきました。そして紹介してもらった仕事を通じて、自分の特性を疑うようになりました。Lobinさんの恩師は最初、Lobinさんが発達障害だとは信じていませんでした。しかし結局、Lobinさんに強く押された恩師が紹介した専門医によって、Lobinさんは自閉スペクトラム症だ、と診断されました。
精神疾患や発達障害の特性ゆえに、数多くの生きづらさを抱え、悩み、苦しみ、人によっては生きるか死ぬかの極限状態から生還した者を、「サバイバー」と呼びます。前述のドナさんと後述の方も、サバイバーに当たります。私の場合も、母を含む心強い味方に恵まれましたが、いじめや不登校、自己肯定感の低下、障害者でも健常者でもない自分の立ち位置に対する孤独感などにも苦しみました。そして別の機会に記しますが、薬の副作用や人間関係の悩みの影響からか、自分が望まないはずの「死のイメージ」や、「誰かを傷つけるのではないか」という不合理な恐怖に足を引きずられそうになった時期を乗り越えて、幸い今は元気に生活しています。
発達障害を生きるという意味
最後は、天咲心良さんの『COCORA 自閉症を生きた少女』を紹介します。心良さんの著書は現在小学校編から思春期編まで出版されています。心良さんは自閉スペクトラム症などの発達障害があり、作中には別人格のものらしき幻聴と会話しているような記述もあります。心良さんは、ただ出来事を記すのではなく、彼女の瞳から見た不思議な見え方を描写し、どこか幻想的でおどろおどろしい世界を感じさせます。また周囲から受けた暴言の文章は太文字で記されているなど、読み手にも強いインパクトを与えます。心良さんが海外留学したエピソードもあるため、同じく留学経験のある私は親近感をいだきました。
親による心理的虐待(人格や言動の否定、きょうだい間の差別、支配的な対応など)のほか、いじめや先生によるスクール・ハラスメント(教師によるいじめ、体罰、嫌がらせ)を受けた心良さん。心良さんは留学したものの、英語や学力の向上には繋がらず、人間関係のトラブルもあったため帰国せざるを得ませんでした。そして心良さんの両親は、海外留学の中断を心良さんのなまけとわがままで片付けました。しかも、海外留学は心良さんが望んだものではなく、両親の気まぐれで行かされたにもかかわらず。私自身も小学校でスクールハラスメントやいじめを受けて不登校になり、その経験がトラウマとなって自己肯定感や安心感の低下に苦しめられました。苦しみというのは他人と比較するものではありませんが、著書のインパクトの強い描写から伝わるとおり、彼女を今もさいなむ苦痛は私が受けたものとは比べ物になりません。
心良さんはどうしようもない奴だ、と言われたに等しい暴言にうちひしがれました。著書を読んでいく中、私は「どうして心良さんが傷ついている、と分かろうとする人が一人も居ないのか」、と胸を痛めました。しかし、作中でも記述されていますが、心良さんは自分の苦しみを上手く表現できませんでした。心の底では深く傷ついているのに、表情はへらへらしていたため、誰も彼女の想いには気づきません。発達障害を生きる、ということは他の人に理解されづらい「孤独」と「苦しみ」と向き合っていくことなのかもしれません。
まとめ
今回は、女性の発達障害者の著書に注目しました。発達障害の多くは、自分を客観的に振り返ることが苦手な方が多いと聞きます。しかし、そういった本来の考え方をくつがえすようなインパクトと心打たれる文章、自分を取り戻して生きることの大切さが、どの著書にも強く表れています。最近は技術の発展により、パソコンで文字を打つ機会が増えています。手書きに苦痛を感じる発達障害者にとって、パソコンは文明の宝であり武器にもなります。発達障害者の方で、是非自分の熱い思いと人生を文字にしたい、というのであれば、「文字を打ってみましょう」。
最後までご拝読ありがとうございました。
参考文献
・ドナ・ウィリアムズ(訳:河野万里子)(2000)『自閉症だったわたしへ』新潮文庫
・Lobin.H(2011)『無限振子 精神科医となった自閉症者の声無き叫び』協同医書出版社
・天咲心良(2017)『COCORA自閉症を生きた少女 1 小学校 篇』講談社
・東田直樹(2016)『自閉症の僕が跳びはねる理由』角川文庫
・学校でのいじめ「スクールハラスメント」「アカデミックハラスメント」について
http://filia-blog.com