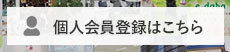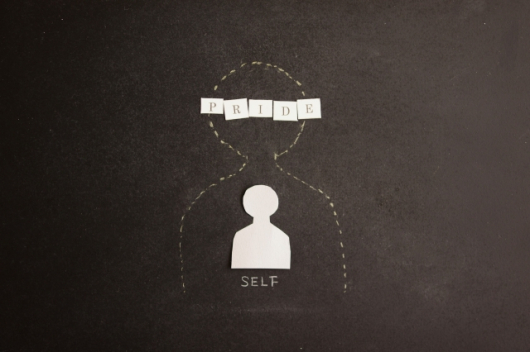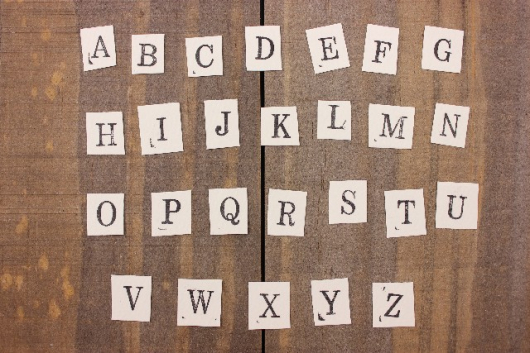映画の中の障害者(第2回)「ジョゼと虎と魚たち」
エンタメ
Photo by Geoffrey Moffett on Unsplash
分岐点の日本映画界
日本映画界のセクハラ・パワハラが大きな問題となっています。昨年の小山田圭吾のオリパラ開幕キャンセルとも同じく改めて感じたのは、サブカルチャーを覆っていた「反道徳がイケてる」な風潮です。戦後まもなくから、文化全般で坂口安吾や石原慎太郎の諸作をはじめ、真に生きるためには反道徳的であることが長らく称揚されていました。一見非倫理的なものが、ウソまみれの社会よりも真実の愛や幸福に近い・・・映画では大島渚、若松孝二、井筒和幸などの無頼派監督があげられるでしょう。それ自体は切実であり、表現はそれを求めるものであって欲しいのですが、敗戦・復興からの個人主義の形成という変遷から必然の結果であったとも言えるでしょう。
ただその後、(当然真に生きるのは困難だから)取り分けサブカルチャーでは、反道徳が反権威と結びつき自己目的化してきて、あらゆる欲望の解放が善となるハラスメントはびこる土壌になっていったと考えられます。そこでは表現の自由を盾に、日頃うちに秘めた攻撃性を解放できる場と錯覚する者もあり、個人の尊厳は蔑ろにされ、弱者へ寄り添っているようで突き放した冷酷さも散見されました。
しかし、近年日本の経済的地位が転落していき、もろもろ世界基準に合わせていこうと社会が変化していく中で日本映画界でも負の側面が明るみになっていると言えるでしょう。実際、商業で活躍中の監督と最近話す機会があったのですが、この10年ちょっとで制作現場も大きく変わり「大声を出す」「罵倒する」など攻撃的な言動は許されない環境になっているとのことです。ネットフリックスなどの制作現場でも撮影前にハラスメント防止研修(リスペクトトレーニング)が取り入れられています。そういった制作環境が個々の作品内容にも影響を与えて、今までなかったような視点・アプローチの優れた作品が次々生まれています。(海外では「プロミシング・ヤング・ウーマン」など、日本映画もこの流れでどんどん増えてくると思います)
前置きが長くなりましたが、今回そういった文脈・変遷を踏まえて日本映画で「障害者」がどう描かれてきたかを下肢麻痺で車イスの女性が登場する「ジョゼと虎と魚たち」の実写版(2003年)・アニメ版(2020年)を基に2回に分けて考察をしていきたいと思います。 ※ネタバレあります
田辺聖子の原作:この社会の片隅で
「ジョゼと虎と魚たち」は田辺聖子の1984年出版の短編作品です。あらすじをウィキペディアから抜粋します(文末に全文リンク有)
下肢麻痺の山村クミ子はジョゼと名乗り、生活保護を受ける祖母と二人暮らし。ある夜、祖母が離れたすきに何者かがジョゼの車椅子を坂道に突き飛ばす。車椅子を止めたのは大学生の恒夫だった。恒夫はジョゼの家に顔を出すようになる。ジョゼは恒夫を「管理人」と呼び、高飛車な態度で身の回りの世話をさせる。
(中略)
恒夫はジョゼと籍も入れず親にも知らせない結婚生活を続けている。ジョゼはゆっくり料理を作り、洗濯をして、一年に一遍二人旅に出る。ジョゼは「アタイたちは死んだモンになっている」と思う。ジョゼにとって完全な幸福は死と同義だった。
世間の価値観とは別の幸福を探求した優れた小説で、そのモチーフとしての「車イスの女」。この退廃的なラストも含めて、80年代日本における障害者の立ち位置を読み取ることができます。特に結末は、映画版・アニメ版それぞれ大きく異なるので、そこを中心に考察していきます。
実写版:障害者という存在の重さと軽さ
その原作を踏まえて2003年に犬童一心監督、妻夫木聡と池脇千鶴が演じて映画化されました。まず私は実写版については否定的な立場です。原作通り、障害者と健常者の恋愛という古典的な設定ですが、日常のささいな情景や空間を丁寧に描写することで平坦になりがちな物語を多面的に膨らませることに成功しています。ジョゼのキャラもわがままだったり恒夫も大学生らしく行き当たりばったりと紋切り型の人物描写を周到に避けています。
しかし映画は終盤、社会人となった恒夫はジョゼが負担になって別れ、上野樹里演じる健常者へ乗り換えする設定が加えられています。その描かれ方と消費のされ方に前述のサブカル特有の陰湿さを感じるのです。もちろん、逃げた後に恒夫が罪悪感で嗚咽するシーンはあります。しかし、ジョゼは恒夫を許し(エロ本のお土産付き)、自立して生活する姿を映し、くるり”ハイウェイ”をバックにエンドロールへつながり包み込むようにして映画は終わります。
この映画が製作されたのは2003年です。原作は1984年。その20年で障害者を取り巻く環境は大きく変わりました。バリアフリーが進み、乙武洋匡が既存の価値観をぶち壊していた時代。そんな中、「下肢不自由」という障害でびびって逃げる主人公という前時代的な設定に唖然としました。
100歩譲ってあるある話だとして、人間の心の弱さを描きたいのであれば、ジョゼをあんな都合よく描くべきだったのでしょうか?一人になったジョゼが、また性犯罪者に胸を触らせてゴミ出ししてもらうのか、それもできずにゴミ屋敷になるのか、精神のバランスを崩して宗教にすがるという、ありそうなリアリティは描かれていません。もしくは愛した恒夫が逃げざる得ない社会構造の問題にジョゼが気付き、変革に目覚めて市議選に出馬するという想像力も、二人の生き生きした暮らしをネットで発信して、世間を変えていき、家族・親類に結婚を認めさせるという想像力もありません。もちろん時代が変われど変わらないものもあります。ただ、その現実を踏まえて何を描いているのか?どうあって欲しいのかが重要ではないでしょうか?
しかし、実写版には差別を受け入れて、身の丈に合わせて生きていくというものしか私には感じられませんでした。うがった見方をすれば、障害者が不幸な存在であって欲しいというサブカル界隈(引いては日本社会)の願望に合わせて、商業的にも原作にはない結末に落ち着いたとも考えられます。実写版は、未だに障害者への「重たい存在でありながらそれゆえの尊厳の軽さが反映された前時代的な想像力の作品だったと言わざるを得ません。 (次回へ続く)
参考サイト
ジョゼと虎と魚たち(Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org
ジョゼと虎と魚たち(実写版予告)
https://www.youtube.com
プロミシング・ヤング・ウーマン(予告)
https://www.youtube.com